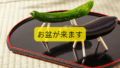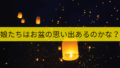いよいよお盆になりました。昨日は墓場まで先祖霊をお迎えに行ってきましたが、暑くて暑くて大変でした。暑くなる前に行こうと思っていても、朝起きた時から暑い場合は一体どうすれば良いのでしょうか。
わざわざ提灯を持って行くわけですから、夕方日が落ちてから出かけても良さそうですが、我が家の夕食は夫の希望で遅くても6時半。夫自体は5時前から晩酌を始めますから、日が落ちてからのお迎えなどあり得ないです。
もっとすんなり先祖を迎えたいが
もうこの家(夫の実家の敷地内)に住みだしてから30年以上経っているので、いい加減お盆に慣れてもいいような気がしますが、私は毎年『どうすればいいのか…』と思っています。
まずお迎えに行くのに、墓に供える花を買います。花を買って一度家に戻り、仏壇に花を活けてから墓場に行きます。これ、前日に買っておけば良いかも…と思うのですが、暑い季節のことです。少しでも長持ちさせるために、当日の朝、買った方が良いだろうか?とも思います。
毎年、どちらにしようかと悩んだ挙句、お盆の当日になってから慌てて花屋に行くことを繰り返しています。まあ、お盆に入ってから花を用意するのは、別におかしなことではないようです。だって、私が花を買いに行くと、ほかにも客がいますから。
墓に行くと花と米を供え、線香をあげます。毎年、線香になかなか火がつけられない(一束に火をつけるのは難しそうです)と、夫の文句を聞かなくてはなりません。
線香を2本残し、提灯のろうそくに火をつけて家に帰りますが、このろうそくの灯が先祖の霊で、消えないように細心の注意を払って、持って帰らなくては(お連れしなくては)なりません。
灯が消えるとまた夫がうるさい(私は消えたらまた、そこで新たに火をつけてお茶を濁せば良いと思っている)ので、私もかなり神経を使います。
自宅に到着したら、持って帰ってきた線香をあげ、提灯の灯を仏壇のろうそくに移して、無事に先祖霊をお連れしたことになります。そこまでやると、達成感はもちろんのこと、疲労感まで覚えます。
我が家でお盆に使う提灯
今年は一度も提灯の灯が消えることなく、自宅にたどり着きましたが、これは提灯に開いた穴を養生テープでふさいだからではないでしょうか。お盆のお迎えに使う提灯、我が家の地域では「こんばん提灯」と呼ばれるものを使っています。
白地に黒い縁取り(縁取りの部分に穴が開く)をした赤い文字で「こんばん」と入っています。なかなか買い替えるきっかけがなくて、穴が開いたのをそのまま使っていたのです。スーパーやホームセンターでもこの提灯は売られています。
今年、買い替えようかと思ったのですが、夫がスーパーで売っている提灯を見て「これ、紙じゃないよね。プラ製品だ。なんか嫌だな。安っぽいよ」と言ったので買うのをやめました。
安っぽいプラ製品を使うのか、穴を継いだボロ提灯を使うのか…なかなか苦しい選択ですが、お盆が終わったらまた忘れてしまうのでしょう。
ネットで調べるとこんばん提灯のこんばんとは、あいさつの「こんばんは」と同じ意味だとか。あいさつとともに、先祖霊を自宅まで案内するための提灯なのですね。
案内するために使うだけなら、ろうそくの灯が消えても大騒ぎする必要もなさそうです。私としてはこちらの説を採用したいと思います。先祖の霊を連れ帰る乗り物として使うのであっても、道案内するために使うとしても、穴は開いてない方が良いでしょうが…
この提灯があるせいか、我が家の地域では迎え火などの風習はありません。お盆の風習、地域によっていろいろ違うんだろうな~、などと考えていると、それだけで趣きを感じます。
趣きを感じるには、やはり自分の家のお盆くらいは、すんなりと行えるようにならなくてはいけないですね。夫と私が亡くなったら、娘たちが同じことをするとは思えないので、もうすぐ我が家のお盆は終わりになるのかな。
そう思うと、残り少ないお盆をじっくりと味わいたいような気もします。来年のお盆は頑張る!つもり。
にほんブログ村
にほんブログ村