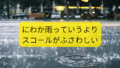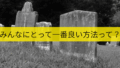しばらくブログを書かないでいる間に、お墓の掃除を終わらせました。結局夫が一緒に掃除をしてくれたので、いつになく念入りに掃除をすることができました。
例年は草を取るだけで精一杯(暑くて疲労困憊となる)。花立や墓石はほとんど手付かずだったのです。特に墓石を久しぶりにきれいに拭けて、本当に良かったと思います。
共同墓地には古い墓石も
何度もブログに書いていますが、我が家の墓は地域の共同墓地にあります。ずっと同じ墓地を使い続けているため、中には驚くほど古びた墓石も…この地域で生まれ育った夫も「これは誰の墓なんだろう?」などと言っていました。
墓石をよく見ると大正という元号が読み取れます。つまり100年以上前の墓石です。100年以上前の墓石は、石そのものが風化していて、ちょっとした地震や大雨で崩れるのではないか、と思われます。
もし、崩れたときにたまたま傍に人がいたら…とんでもない事故につながりかねないな、と思いました。
崩れそうなら修復すれば良いのですが、近しい親族が生きていたらすでにそうしていたわけで、今大正時代のままの墓石がそのままになっているのは、面倒をみる親族がいないからに違いないでしょう。
墓石を建てた人も、まさか100年以上経ったのちに、誰にも面倒を見てもらえなくなっているとは、夢にも思っていなかったはずです。しかし、何しろ生まれる子どもの数が減っています。お墓の面倒を見られる人はこれからも減り続けるでしょう。
大正時代の墓石に、我が家の墓の行く末を見た思いがしました。
お墓問題は今が一番大変かも
地域の共同墓地は昭和40年代までは土葬でした。墓石の下にお骨を収めるようになったのは50年代以降だそうです。夫が言うには、父は土葬で、母は火葬だったと言っていました。
土葬の場合、長い年月をかけて亡くなった人は土に還ります。だから、現在墓じまいをするときのように、お骨をどうしようか…という心配はありません(と言うかできません)。
そうすると墓石が朽ちたらそれで終わりだったわけですね。それはそれで合理的だったのかもしれないな、と思いました。
現在の墓石の下の、お骨を収めるスペース(カロートと言うそうです)に骨壺を置く方法では、いつまで経っても、お骨はそのままです。この方法を取るようになったばかりに、余計にお墓の面倒を見る人の存在が必要になったような気がします。
まあ、お骨は最終的には土にまけば良い、と我が家の菩提寺の住職さんは言っていました。しかし、これ、自分で勝手にやったらまずいですよね。
我が家は当分このままでいくしかないのか?とも思います。何しろ私と夫が入る墓が必要ですから。
しかし、私と夫が死んだら、あとは娘たちしかいないです。取り合えず娘たちは我が家の墓に入るとしても(誰が入れるんだろう?)、さらにその後はもう無縁仏になるしかありません。
本当は墓じまいをした方が良いとわかっているが…
本当は墓じまいをして、自分たちは樹木葬や散骨を考えた方が良いのだと思います(娘たちのため、だけではなく、墓地のほかの家の墓のためにも)。
ただ、それには資金が必要ですから、いつも考えはそこで行き詰ってしまいます。ああ、今年も無事に墓掃除が終わって良かった、良かった…、取り合えず肩の荷が下りた、などと思っていますが、これは現実逃避そのものです。すぐにまたお彼岸が来て、同じことを考えさせられる…
実家の母は父が亡くなったときに、墓がないことに悩み、考え抜いて霊園の一区画を購入しました。よく私は母から「ゆみこねこのところはもうお墓があるんだから、いいわね~。何の心配もないじゃない」と言われたものです。
しかし今、私は墓を作ったが故の心配の方が、大きいような気がしています。私の実家では母の存命中、弟は結婚しておらず、墓を作っても入るのは父母と弟の3人だけだと母もわかっていたはずです。
いくら永代供養を申し込んであるとしても、墓だけがずっとある状態をどう考えていたのでしょうか。現在弟は結婚していますが、50歳を過ぎていたため、子どもはいません。
墓をめぐる環境は変わらず、無縁仏が決定しています。母はそれでも良いと思っていたのか…今でも私には疑問です。やはり最初からお墓など作らず、樹木葬が良いと思います。決まった場所で手を合わせることもできますからね。
にほんブログ村
にほんブログ村